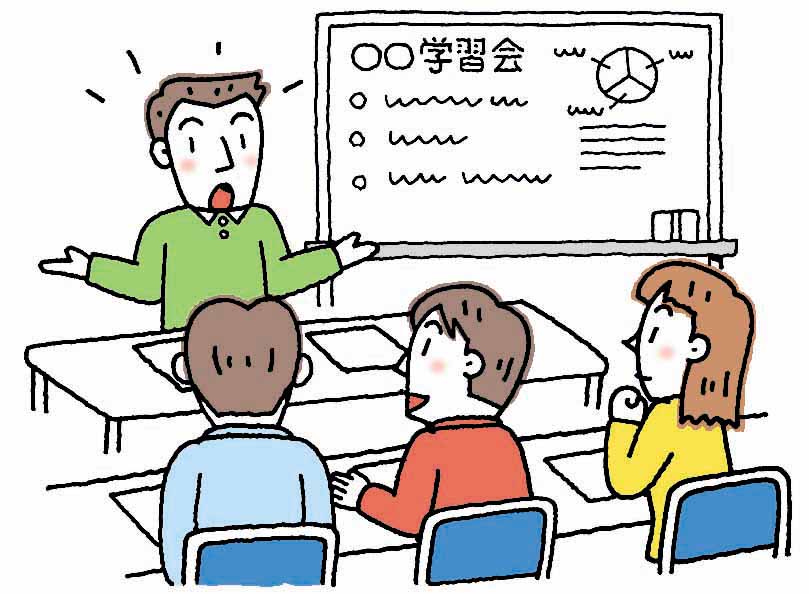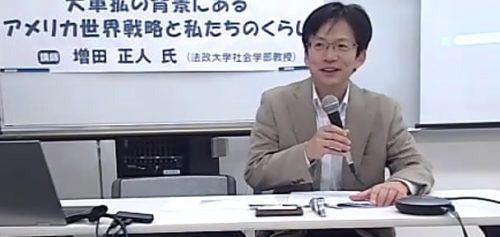2024年7月21日、静岡労政会館にて静岡県学習協の第52回総会と記念講演が行われました。記念講演は 「新版 戦後日本史」学習会の公開講座を兼ねて、「 歴史の転換点を戦後史から考える」と題して、山田敬男氏(労働者教育協会会長・現代史家) が講演しました。

1 どのような視点で見るのか
①世界のなかの、アジアのなかの日本
日本の近代化は、アジアに対する侵略戦争と植民地支配を条件にして推進され、「15年戦争」で破綻しました。戦後の日本は、アメリカに従属し、アメリカのアジア戦略に従って、アジアとの関係をつくってきました。日本社会の変革は、アジアの平和と民主的国際秩序構築の運動と連動して行われます。
②日米関係、対米従属を重視
講和条約と日米安保条約の二つの条約の調印(51年)によって、日本は形のうえで「独立」しますが、事実上はアメリカの従属国になります。安全保障問題だけでなく、経済や生活、社会のあり方まで、安保条約によってアメリカに従属するようになっています。
③憲法と戦後民主主義をめぐるせめぎあい
④社会運動、人民のたたかいを重視
2 戦後日本の出発(1945~1952年)
①戦争の終結と民主化
45年7月「ポツダム宣言」が発表され、連合国は日本の無条件降伏を求めてきました。この宣言は、反ファシズム連合国の綱領的宣言というもので、日本の軍国主義の一掃、連合国の占領、日本軍の完全な武装解除、戦争犯罪人の処罰、民主主義の徹底などが明記されていました。
占領期において、前半はポツダム宣言にもとづいて民主化が行われますが、後半は、冷戦の激化のなかで、民主化が中断し、日本を反共の防壁とする占領政策に転換します。
新憲法はアメリカに押しつけられたものではありません。第一に、第9条は、天皇制を守るためには、軍事力の放棄という厳しい条件が必要とされるほど、当時の国際社会の反ファシズム反軍国主義の世論は強かったのです。第二に、政府は国民主権の明記に最後まで反対しました。日本の民主的諸勢力の奮闘と極東委員会の決定の結合によって、憲法に国民主権が明記されたのです。第三に、憲法第25条の生存権規定もこの議論のなかで付け加えられたのです。
②民主化の中断と日米安保体制
中断と弾圧(政令201号)、
分裂(産別民主化同盟の発足)、
謀略(49年の三大フレームアップ)
③日米安保体制と基地国家日本
冷戦、朝鮮戦争、日米安保体制の成立
3 高度成長と戦後民主主義(1950年代前半~70年代半ば)
①「戦後民主主義」の再発足―逆流への危機感、60年安保
総評はアメリカの朝鮮戦争への介入を支持していましたが、51年の第2回大会で、「平和四原則」(全面講和、中立、軍事基地反対、再軍備反対)を採択します。反共親米からの転換といえます。いわゆる“にわとりからアヒルへ”の転換が始まったのです。
②「人類の生存の危機」の提起
54年、アメリカはビキニ環礁で水爆実験を行いました。このとき、焼津のマグロ漁船第五福竜丸が「死の灰」をあび、23名の乗組員は放射能に侵され、無線長であった久保山愛吉が後に死亡します。こうしたなかで、自然発生的に原水爆禁止を求める署名運動が始まります。
また55年、イギリスの哲学者ラッセルとアメリカの核物理学者アインシュタインは核戦争の危険を警告する宣言を出し、「人類の絶滅」の危機を指摘しました。こうして、階級や民族の問題とともに「人類」という視点が提起されたのです。
③60年安保
59―60年にかけて史上空前の安保闘争が展開されます。この大闘争を推進したのは、安保改定阻止国民会議でした。これには社会党、共産党、総評など134団体(後に138団体)が参加しました。日本国民は、新しい安保条約の成立を阻止できませんでしたが、アイゼンハワー米大統領の訪日阻止と岸内閣の退陣をかちとりました。
④高度成長と日本社会の変貌
55年から73年の19年間のGNP(国民総生産)の実質平均成長率は、10%近いという驚異的な伸びでした。高度成長によって、産業構造が大きく変化し、日本は重化学工業国になります。高度成長のなかで、少数の巨大企業が形成され、経済力を集中し、日本経済を支配するようになります。
日本の階級構成が激変し、労働者中心の社会に移行しました。人口が都市に集中し、50年から70年の20年間で、約4000万人が都市に集中したのです。国民生活のあり方が大きく変化し、アメリカ的生活様式の導入が本格化したことです。耐久消費財の大量普及によって生活様式の「近代化」が進行します。
⑤現代的貧困と変革の可能性
70年から74年にかけての春闘は、年金などの社会保障や物価問題などの国民的課題に真正面からとりくもうとしており、日本社会の民主的再編に労働組合運動が挑戦を開始したことを示していました。これまでの〝貧困論〟の枠組みでは解決できない都市問題や公害・環境問題などの社会的問題の出現という現実がありました。国民春闘への発展は、戦後日本の労働運動の企業内主義、経済主義という歴史的な問題点の克服の可能性を生み出していたといえます。
大きな契機は67年の東京における美濃部革新都政の実現です。その特徴は、社会党、共産党、民主主義諸勢力が「明るい会」をつくり、政策協定、組織協定を結んで持続的な共闘体制で闘ったことにあります。75年には、全国の革新自治体総数は205になり、全人口の約43%がそのなかで生活するようになります。
高度成長期に日本社会は、大企業中心の都市型社会に転換しました。大企業本位の経済成長のなかで、「競争型社会」がつくりだされたのです。そしてこの競争のなかで、憲法で保障された民主主義と人権が形骸化されることになります。
また、この時期の多様な社会運動を通じて、憲法の民主的規範が国民のなかに浸透し始めます。べトナム戦争とそれに抗議する反戦運動のなかで、日本国民の平和意識が成熟し、憲法第9条が深く国民のなかに定着します。また、朝日訴訟、公害裁判闘争、家永教科書裁判などのなかから、生存権、環境権、教育権などの考え方が国民のなかに浸透し始めました。
4 新自由主義的「改革」と軍事大国化の危険性(1970年代後半~2020年ぐらいまで)
①「社公合意」と革新統一の破壊
78年、「日米防衛協力のための指針」(=ガイドライン)が決定されました。ソ連の「脅威」に対する「日本有事」の具体化とともに、「極東」を対象とする日米共同作戦体制構築を目指すものでした。
80年、社会党と公明党の「連合政権についての合意」(社公合意)がなされました。政権協議の対象から共産党が除外され、政策的に当面、安保条約と自衛隊が容認されました。この社公合意締結前後に、革新統一が壊され、革新自治体が後退していきます。
②中曽根内閣
中曽根首相の“戦後政治の総決算”は、経済優先の自民党から、国家優先の権威的な自民党への転換の宣言であり、21世紀になって小泉政権や安倍政権に継承されていきます。
高度成長の終焉によって、ケインズ主義にかわって新自由主義の潮流が登場しました。新自由主義は、経済的には弱肉強食の市場経済万能主義を、政治的には民主主義の抑圧・形骸化という反動的な性格を持っていました。
③90年代の労働運動の大転換と社会党の事実上の解党
89年、総評が解散し、連合が発足しました。日本の組織労働者の65%を占める日本の労働組合運動史上最大のナショナルセンターでした。こうして同盟・JC系の右翼的潮流が戦後初めて労働運動の主導権を掌握することになります。
同日、「たたかうナショナルセンター」全労連が結成されました。58年に産別会議が解散して以来、30年の空白がありましたが、その空白を埋めるたたかうナショナルセンターがついに実現したのです。
94年、社会党は臨時全国大会を開き、中立・非同盟路線を放棄して安保条約と自衛隊を容認することを公式に認めます。96年、社会党は社会民主党に党名を変更し、事実上の社会党の解党でした。
④日米同盟のバージョンアップ
91年にソ連の崩壊により、冷戦が終わると、第2次ガイドラインが97年に締結されました。「日本有事」にかわり、キーワードが「周辺有事」になります。15年4月に第3次ガイドラインが締結され、「世界中の有事」に対応することになります。15年9月に安保関連法が強行されました。
⑤労働政策の根本的転換
95年の「新時代の『日本的経営』」に示されるように、一方で、成果主義的労使関係が導入され、従来にない競争によって、労働者が分断され、長時間過密労働が深刻になります。他方で、専門職から一般職まで非正規雇用労働者が急増し、職場における自由と権利が空洞化されます。こうした職場の変化のなかで、多くの労働者は仕事と生活のゆとりを失い、つきあいが難しくなり、労働組合運動の団結の基盤を崩していきました。
⑥歴史修正主義運動の本格化
97年、「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」「日本会議」「日本会議国会議員懇談会」が発足します。“靖国”派勢力の総結集です。
⑦新自由主義的「改革」の本格化と軍事大国化に向けて
小泉内閣は、新自由主義的な「構造改革」を全面的に実行するものでした。
安倍内閣は、「海外で戦争する国」と「世界で一番、企業が活躍しやすい国」を目指してきました。
⑧新自由主義のもとでの青年たちの苦悩
いまの青年たちは、長くつづいた新自由主義のなかで、孤立したバラバラの状態に置かれ、苦しさを感じても、それを自分が悪いと思い込み、「助けて」と社会的に発信できにくくなっています。「自己責任論」の威力です。
5 いま問われていること
①「人類の生存の危機」の深刻化
核兵器の廃絶や気候危機の克服など人類の生存を維持する独自の努力を成功させなければ、未来社会の展望が生まれてきません。現代の労働者階級と民衆の階級闘争は、人類史的運動を発展させながら、「体制の変革」をめざすという特質をもっています。
②戦争の危険が現実のものに
戦後、日本政府は憲法第9条があるため、海外での武力行使、集団的自衛権の行使、国連への軍事協力はできないとしていました。このルールが踏みにじられ、日本の「先制攻撃」による戦争の危険性が増大していることに日本の平和の最大の「脅威」があるのです。
③政治変革の歴史的チャンス
日本の平和と安全を確かなものにするには、対米従属的な自民党政治を根本から変えなければなりません。その主体的な推進力は、「市民と野党の共闘」の再構築にあります。市民や労働者の要求にもとづく、国民的たたかいと「共闘」を求める世論の高揚、「共闘」推進勢力の政治的組織的影響力の強化、魅力的な活動家集団の育成が必要です。
日本の階級闘争の担い手にとって、「個人の尊重」を基礎に、憲法と民主主義の理解を深めることが極めて重要な意味を持ちます。
7月12日、静岡市内において「学習の友」7月号を使用した読合せ学習会を開催しました。
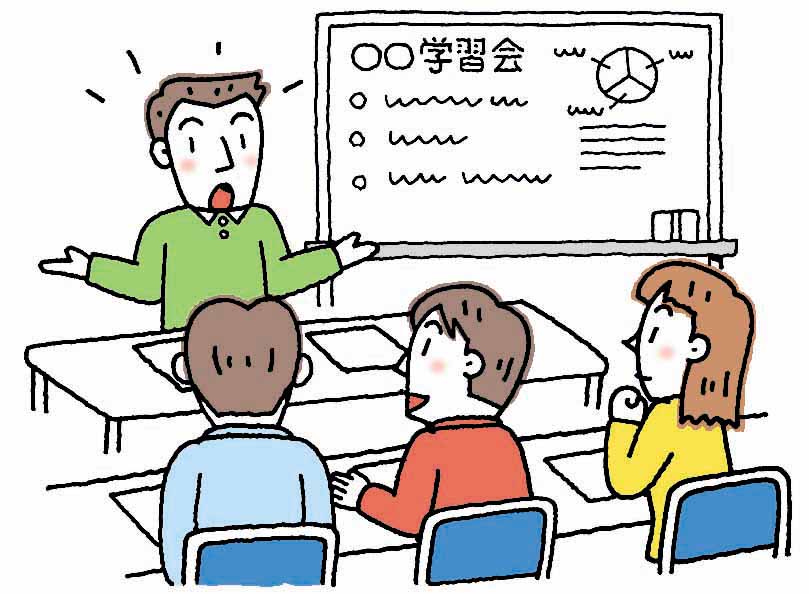
7月号の特集は「核廃絶へ 世界のなかの日本の運動」です。今回は、「核兵器のない平和な世界を―世界は立ち上がっている」(土田弥生日本原水協事務局次長)と、「被爆者とともに、核兵器のない平和で公正な世界を原水爆禁止運動の歩みと草の根運動の役割」(高草木博日本原水協代表理事)の2つを読合せ討論しました。 土田氏の記事は、主に核兵器禁止条約の署名、批准国拡大の経過を示すとともに、被爆国でありながらそれに向き合わない日本政府を批判します。そして、「核兵器の問題は、地球上に生きる一人一人の問題」とし、8月の原水爆禁止世界大会への参加を訴えています。高草木氏は、日本の原水爆禁止運動の歴史を紹介し、世界の反核平和運動の誕生と発展に与えた影響をも明らかにしています。そして、この流れの前進についての展望を語り、2024年世界大会へ結集し、核兵器禁止の努力を続けようと訴えています。 討論では次のような意見がありました。 「昨年の国連総会での『核兵器禁止条約』決議は、・・反対の内訳をみると、・・アジアでは韓国、日本だけとあるが、中国は反対しなかったのか?」「棄権をしたのかも」「最近長崎に行ったが、爆心地は天候のため山の方になったようで被害は広島より多少小さかったとのことだが、多くの人が亡くなっている。資料館へ行ったが良かった。」「核戦争になって『核の冬』になるとあるが、それは知らなかった。」「昔よくテレビでやっていた。」「太陽光線が届かず、地球の温度は下がって野菜が育たなくなる。食料が無く人類は死ぬということだ。」「核は使わずに、温暖化をくい止めることはできないものか。」「無理だね。」「地球史のスケールでいうと今は氷河期に向かっているというけど。」「氷河期は何万年単位で繰り返しているようだ。青森の三内丸山遺跡は、遺跡のすぐそこが海だったようだが、今は海はない。」「当時は温暖だったということだね。」「石川の地震で隆起し港が港でなくなった。自然災害で火事もあったが一瞬で住んでいる所を変えざるを得なくなるってことがよく分かる。」「(高草木氏の記事のグラフについて)これはアメリカ国民の原爆観だが、55歳以上だと半分は原爆投下が正しかったと回答しているね。」「戦争を直に知っている人が多かったからか。」「スミソニアン博物館では、今も投下を支持する文言があるね。」「日本でも朝鮮・満州の植民地化をしたおかげで、現地の人は『生活が良くなった』という主張をする人がいた。」「湯川博士のノーベル平和賞は知っていたが、日本被団協も平和賞を受賞したのは知らなかったね。」
6月14日、静岡市内において「学習の友」6月号による学習会が開催されました。
今回は6月号の特集記事の「物価高・株高・NISA-日本経済の今を読み解く」(山田博文群馬大学名誉教授)を読合せ討論しました。 国民生活は苦しいなか株式市場は大活況で、株価は戦後の最高値を記録しています。大株主と国民との資産格差が更に広がっています。特に近年情報通信手段(ICT)の発展により、証券売買取引が超高速となり不正や金融犯罪が発生しやすくなりましたが、日本では規制、行政処分が甘くなっていると云います。その上で、「日本銀行による株価下支え政策に支援され、日本の株式市場は、世界の投機マネーの草刈り場になっている」と指摘をします。そして、「最近の株高は、日本経済の成長や企業経営の好転ではなく、ドル高=円安という為替相場が主な背景になってい」ると明らかにします。日銀はすでに時価総額70兆円ほどの株式を買い入れています。日銀保有株が下落すると、円安・円暴落を招き、輸入物が暴騰し国内物価の、国民生活が直撃を受けます。そうしたなかで政府は「資産運用立国」を掲げ、株式投資・不動産投資を勧め、資産を持たない多数の国民を切り捨て、一層の格差拡大の政策を推し進めています。家計は火の車状態なのに、政府は有効な政策を打っていません。いま大切なのは、「国民生活関連予算を拡充することです。」と指摘をします。 討論では次のような意見がありました。「今日ニュースであったが、『日銀が国債買入れ額を減額する』とあったが、経済にはどういう影響があるのか。」「今のところどれだけの金額かわからないが、影響は限定的と思うがね。」「それは日銀が金融を正常化しようとしているということだよね。」「日銀の『異次元の金融緩和』をやめて元に戻そうとするが、それをやりすぎると不況になるので、調整しながやっているということだ。」「ただ実体経済が回復しないから、思うようにはならないのではないか。」「日銀が銀行から国債を買わなくなると、国債は売れなくなる。そうすると国債の価格が落ちてくる。落ちてくると金利が上がる。金利が上がると金利負担を政府はできなくなる。で大変になってくる。だから極端な買入をおさえるのはできないのではないか。」「景気が良くなれば、需要が増え金利が上がる。こうなれば好循環となるが、景気回復がないままでは負担だけだ。」「とにかく実体経済を回復させないとだめだ。」「最賃低迷で消費不況ではだめということだ。」「日銀の動きは、おそらく海外向けのポーズだと思う。ちょっと変えて様子を視るということだ。」「一般的には金利を上げると株価は下がる。だけど今の日本は逆の動きになっている。政府の政策を超えた海外の投資家の動きがある。日本の経済事情がそういうところに来ている。本気になってかえれば良いが、『どうせ日銀が買い支えてくれる』と、足元をみられているということだ。政府はわかっていてもやりようがないようだ。」「れいわ新選組の主張が『MMT理論』で、お札をどんどん刷れば良いという立場だ。」「物価が上がらなければどんどんお札を刷って、物価が上がれば限界というものだ。」「今そういう経済学者がネットで発信している。」「もともとはアメリカのサンダースのブレーンの政策だ。」「アメリカの国債と日本のとは違うのだが。ドルは国際通貨だからね。」「記事の参考文献(22ページ)の『国債ビジネスと政府債務大国日本の危機』で山田博文氏は、『MMT理論』を批判している。国債は大企業にとっては大儲けの手段だ。国が安心の元本保障の証券。そういう面を『MMT理論』の者は見ていないといっている。」など、活発な意見がありました。
5月10日(金)、静岡市内において「学習の友」5月号を使った学習会が開催されました。
今月は5月号、特集「若者の今と労働運動」の記事、「青年の実態、青年の課題」(稲葉美奈子全労連青年部書記長)と、「青年が誇りをもって働くために―職場・地域で仕事を語り合う労働組合へ」(植上一希福岡大学教授インタービュー)の2点を読合せ討論しました。読合せの後の討論では、次のような意見がありました。 「いま『将来年金はもらえないよ』と普通に言うね。青年が貯蓄したくなるのは当たり前だ。」「年金の支給時期が繰り上げられる方向だ。」「以前から日本人はよく貯蓄をしていた。社会保障が貧弱だと貯蓄をせざるを得ない。」「私の子は家を建てるのに高額の住宅ローンをしているが、支払いが大変。」「自分の子は、月20万円の給料で原則賃上げはない。それで海外旅行はよく行く。NISAで少し投資をしていると聞いたが、貯金はないのでは?衣食住がまともにできているか心配だ。」「所帯を持っても、子供たちは親とよく買い物に行く。それは親が金を出すからだ。」「若い人はよくディズニーランドや、海外旅行に行きたくさん買物をする。それが楽しみで生きている。」「それでなければ記事にある『30歳くらいで死にたい』という青年の話しのようになる。」「それでは『社会を変えていこう』ではなく、『いかに今を楽しく』という思考になっている。」「30で死にたい人は、将来の年金のことなんか考えないよな。」「それが普通になっている。」 「いまゴールデンウィークが明けたら、たくさんの若者が『退職支援』の会社を通し、仕事を辞める行動に出ている。」「自分の近くの青年も転職している。題が原因のようだ。」「以前の会社は、人を育てようという方針だったが、今はそ」「保育士が集団で退職する事例が静岡市の保育園でもあった。労働環境の問れが放棄されている。行政もそれを変えれない。職場をどう変革するかの問題だ。」「昔はOJTで、仕事をしながら覚えていくよう研修しキャリアを積んでいった。ドイツの労組がキャリア形成の問題をよく取り上げていたと聞いたが。」「ヨーロッパは割とそうだ。イタリアなんかは仕事の資格を労組が与える制度があるように聞いている。」「企業内組合だと難しいね。産別組合なら、転職しても同じ組合員としてキャリア証明できる。」「民間は連合が多い。民間企業の中で、そういうのが求められている。民間の大企業でやっているから、社会に広がる。今は中心の企業が止めてしまっているから。」「公務労働でもキャリア形成の仕組みがあったとは思うが。また、そういう職場の関係で、先輩が労組の活動家で労組のことも受け継ぐ、そうしたこともあったのでは。」
4月12日、静岡市内において「学習の友」学習会が開催されました。
今回は4月号の特集記事、「現代の階級闘争とオルガナイザーの役割」(大屋定晴北海学園大学教員)を読合せ討論しました。著者は、「階級闘争」の意味を確認したうえで「オルガナイザーの今日的役割を考えてみたい」と云います。 結論としては資本主義社会の階級は、資本家階級と賃金労働者階級となります。生産手段の所有をめぐる違いを基本としますが、お金を介するかたちのところが資本主義的な特徴となります。階級闘争は、端的には賃金労働者の労働運動として現れます。そしてそれは、様々な社会闘争と結びいて展開される必要があるとします。しかし、生産手段をもつ側が、政府やマスメディアなどを動かし、暴力的弾圧、思想的な圧力を仕掛け、押させ込もうとします。この点でブラジル教育・哲学者のパウロ・フレイレの主著「被抑圧者の教育学」の内容を紹介します。「抑圧者は被抑圧者に入り込み、被抑圧者に宿っている」と著書の中で指摘します。抑圧者は、抑圧者の「反対話的な文化行動」を植え付けると云います。そこで、フレイレは、これとは真逆の「対話的行動」が必須になると主張します。そして「指導者」の存在を強調します。指導者は、対話的行動の立案、企画、進行を行う人です。指導者は事前準備と訓練をうけたうえで、被抑圧者の対話行動を促し、彼らに労働・生活状況に目を向けさせ、矛盾を気づかせる、助産師役になるとします。これがオルガナイザーです。そして大屋氏は、彼らに求められる3つの役割を明らかにします。①抑制状況を生みだす社会構造の分析・教育。②自らの政治性の堅持。③自身のたえざる自己反省。 討論では、次のような意見がありました。「『パウロ・フレイレ』は、ユネスコの『学習権宣言』を起草した人だ。」「オルガナイザーの役割の『②自らの政治性の堅持』とは、どういうことだ。」「階級性、思想性と同じではないか。」「その人の政治的立場ということか。」「変えていくという立場、いわゆるポリシーを持ってやるということでは。」「社会状況が組織の中にも影響を及ぼすよと云うこと、だがそれを分かって自らを改心することが大事。そうでないと(抑圧者と)同じ事をやると云うことでは。」「第一の役割に、『社会構造の分析・教育』とあるが、なかなか厳しいね。」「今度自治体の青年が、レイバーノーツの大会に行く。この組織の基本的考えがフレイレの思想だ。」「大会というのは、対話のしかたの訓練の場だ。」「それは凄いね。」など、活発な意見交換となりました。
3月8日、静岡市内にて「学習の友」学習会が開催されました。
今回は、「最賃1500円運動の意義、今後の展望」(中澤秀一静岡県立大学短期大学部教員)を読合せ討論しました。2023年最賃は、引き上げ率4.5%引き上げ額43円、全国加重平均額で1004円となったものの、物価高騰に賃金上昇が追いつかない状況が続いており、最賃1500円が「ますます説得力をもってきた」と云います。1500円の根拠は、全労連、地方組織が取り組む「最低生計費試算調査」です。この調査で、①労働者が普通に暮らすためには月額24~26万円が必要。②生計費は全国どこでも大きな差がない、ことがわかりました。最賃制度は、労働基準法第一条「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」と定めており、最低賃金で普通に暮らせることが強調されるべきで、そこに制度の本質や存在意義があると云います。最賃の審議会は議論において「支払い能力論」が強い影響力をもっているが、それは「排除されなければなりません。」と言い切ります。もちろん体力のない中小企業への直接助成等の実現も必要とします。最後に最賃運動のもう一つの目標として、「全国一律制度の確立」も挙げます。2023年制度の見直しにより、4ランクから3ランクに変更しました。根拠をもとにした運動の成果と指摘し、今後も社会の共感を得ながらターゲットを見定めた戦略が重要と云います。討論では、次のような発言がありました。「全国加重平均で千円超えたというけれど、5つか6つくらいでしょ。東京都、神奈川、大阪、名古屋とか人口が多いところのだけだ。」「20ページに税制上の壁が『106万円』とあるが、誤りで103万円だ。」「17ページの最低生計費試算調査の結果表を見ると、必要最低賃金額AとBの中間ぐらいが実態で、1500円~1600円くらいだ。」「静岡は載っていないが静岡の生計費は高かった。」「東京は家賃は高いが、自動車は入れていない。地方は自動車が入るので、都市と地方はあまり変わらないという結果だ。」「18ページの『標準生計費』は随分低い。生活保護基準くらいでは。」「生活保護と最低賃金との整合性を考えているので、今は最賃が高い。」「いずれにしても全部安すぎる。今はチャンスで潮目が変わりつつある。日産の下請けたたきが話題になっている。中小の支払い能力がなんとかならなければ何ともならない。世論が盛り上がってこないから。」「大企業が適正価格で中小に支払うことが必要だ。現実的に引き上げようと思ったら、政府の援助も必要だが、物価が多少高くなろうがそれなりの給料を払った上で、経営が成り立つ利益が出るのでなければ、継続していかない。」「大企業の監視、罰則規定の強化などをしつつ中小への価格の適正化も必要。」「外国には、公正な条件にさせる法規があると思う。」「今でも監視制度はあるが罰金が安い。毎年指摘がされる事態が、見つかっているだけで8千件もある。摘発されれば本来は減っていくはずだが、減らない。」「外国では、中小の直接支援をやったが、日本も提案はしているが、小企業は直接的、中企業は中期的な支援を経営者調査では求めているようだ。1500円となった場合、全体の労働者からの所得税の納税額が増えるが、その分で中小企業に配分すると、社会保険料の金額を賄うことができる。そうした配分の提起もこちらからしていかなければならない。」「フランスが中小企業分の社会保険料を減らして、賃上げの原資の確保をしているようだ。」
2月9日、静岡市内において「学習の友」学習会を開催しました。
今回は、特集記事「要求の求心力で仲間を増やし、要求を実現するために」(竹下武全労連事務局次長)を読合せしました。厚労省の2023年労働組合基礎調査の結果、23年6月末の労組の組織率は16.3%で、昨年より低下しました。日本の労組は「大企業・正社員・男性中心」の構造です。「組織率低下は労使関係におけるパワーバランスが資本の側を強くすることに働いてしまい、労働者の苦難が増してしまいます。」と指摘します。しかし、ストライキでたたかう労組に注目と期待が集まり、労働者を励ましているとも云います。では、労働者が労組に「関心がない(ように見える)のはなぜでしょうか。」と問いかけます。「自分が今抱えている問題、困難さを言ってもいいのかわからない、あるいは受けとめてもらえそうにないと思っているかもしれません。」「これまでの組合のたたかい方が本気に見えないから距離をとっているかもしれません。労働者一人ひとりがどのような困難を抱えているのか、一番の関心事は何かを対話を通して理解し、その要求を実現するために労働組合ができることをひとつひとつ積み上げていく。その姿が労働組合への結集を強める原動力になる」と問題提起をします。そして、全国の労組の経験を紹介します。おわりに、「要求の求心力での組織化と、仲間を増やして春闘をたたかうことが積極的に受けとめられ、23春闘から実践が広がってい」ると云い、24春闘は「こんなに仲間が増えて要求が前進した!」と言い合えるようにしようと訴えます。 討論は今回時間が足りず、十分にできませんでしたが、次のような意見がありました。「『いったんは組合加入申込用紙に記入した新入職員が後日集団脱退したという報告が各地から寄せられ』た、とのことだが、静岡でも聞いてるか。」「・・・?」「三重県の話だが、ある労組でいくつか職場のある中で、一つの職場支部の全員が脱退したと聞いている。」「何かの圧力があったのかな。」「幹部請負的運営がされていて、一般組合員は『入っていても入らなくても変わらない』、との受止をしていたようだと報告があった。」「雇用者数は6千万人くらいいるのか。」「組織率は公務員も入っているが、ここでの規模別組合員数は、企業でと云っているので、公務員は入っていないと思う。」「ちなみに静岡県の組織率は16.5%だ。」など、組織強化の課題をどう克服するのか。今後も考え実践が求められます。
2月3日、「あざれあ」において静岡地区春闘学習会が行われ22名が参加ました。「大軍拡の背景にあるアメリカ世界戦略と私たちのくらし」と題して、増田正人氏(法政大学教授)が講演しました。
日本の大軍拡はアメリカの要求によるものですが、アメリカの世界戦略が中国との関係では、米中蜜月の時代から米中対立という関係に変化してきました。
中国は1978年以降の開放政策で、アメリカ・欧州の多国籍企業を国内に誘致し、相互依存関係を強め、経済的封じ込めができない状況を作る路線を進めました。
またアメリカは1995年のWTO発足を契機に知財重視の世界戦略をとり、多国籍企業化を進める中で高成長を実現するために、アメリカ国内の労働集約的工程を発展途上国に移転し、その生産基盤を提供したのが東アジア諸国、特に中国でした。
中国は世界の工場として、アメリカICT企業の調達拠点となりましたが、製品に占める付加価値部分はアメリカの企業が獲得し、単なる生産の場としては中国経済の発展は望めないという認識になりました。2009年から中国の路線転換が始まり、低賃金と豊富な労働力に依拠した生産から、IT産業等先端産業の保護育成に取り組み、建国100年の2049年までに製造強国のトップをめざすとしています。
2017年のトランプ政権の登場から、アメリカの対中関与政策は転換し、バイデン政権になっても対中封じ込めの強化は変わりません。アメリカの目的は、先端技術とデジタル社会における利益の独占の維持と、中国に対する軍事的優位の確保です。
ただし最先端技術以外の工業製品、資源・エネルギーの生産ネットワークは今までと同じで、米中貿易は2022年に過去最高を更新しています。
バイデン政権の考え方は、気候変動危機に対応する新たな産業技術としてのグリーン・ニューディール政策と軍需産業基盤の確保です。アメリカの軍需産業は、国防上の観点から多国籍企業化してきませんでした。そのため生産コストが高く、それが軍事研究の制約となっています。
アメリカは米中経済の相互依存関係は維持しつつ、中国に依存しない仕組みの構築を図ろうとしています。中国封じ込め戦略におけるカギとなるのが日本です。自衛隊の軍事的強化と基地の運用能力の強化、そして日本の武器購入はアメリカの軍事産業基盤を強化し、さらに日本企業をアメリカの軍事産業に組み込むことにより、アメリカの軍需生産基盤の脆弱性を克服することを狙っています。
もし「台湾有事」が勃発すれば、被害を受けるのは、台湾、日本、中国等の東アジア諸国です。限定戦争にとどまる限り、アメリカや欧州は被害を受けません。アメリカの政策に追随することでは、日本経済や人々の暮らしはますますひどいものになってしまいます。
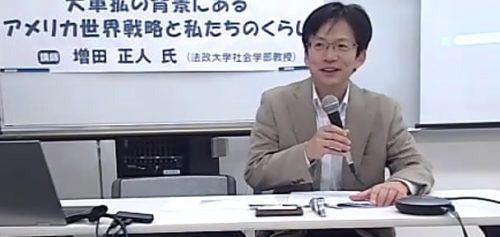
1月12日、静岡市内において「学習の友」学習会を開催しました。
明けましておめでとうございます。「学習の友」学習会は、今年も毎月開催できるよう頑張ります。どうぞ気が向いた時にお立ち寄りください。 今回は1月号です。特集「世界のなかの日本の針路」の記事、「イスラエルによるパレスチナ民衆へのジェノサイドを許すな!即時停戦を―歴史的背景と国際社会・先進国の責任」(栗田禎子千葉大学教授へのインタビュー記事)を読合せ討論しました。 このインタビューでは、ガザ問題の歴史的背景を19世紀のオスマン帝国支配時代に遡り、それ以降の同地域の植民地支配の変遷を明らかにしています。帝国滅亡後、イギリス・フランスによる分割事実上の植民地支配があり、パレスチナはイギリスの「委任統治領」となります。イギリスは欧米からの移民を受入れ「入植国家」化し、「ユダヤ人国家」建設を後押ししました。そして第二次大戦後は、イギリスに代わりアメリカがそれを引継ぎます。そして、パレスチナ人は土地を奪われ、殺され、難民化しているのです。イスラエルは建国以来戦争で領土を拡大し続けてきました。しかし欧米などいわゆる先進国は、これを黙認している状況です。「世界中のすべての国が、いま、歴史の前で試験を受けている」と栗田氏は指摘します。 討論では、次のような意見がありました。 「ドイツがなぜ進攻を認めているのか疑問だったが、そういうことか。(ドイツが犯したホロコーストの被害者が作った国だから、イスラエルに徹底的に寄りそうのが国是)」「ホロコーストを犯した国だからこそ、『止めろ』と言うのが役割だよね。」「国民のレベルではそういう声はあるだろうが、政府の姿勢はそうなってしまう。」「ハマスの攻撃は、イスラエルの諜報機関によって警告されていたが、それをイスラエル政府は無視をしたようだ。それは、わざとやらせたのではないかという指摘がある。なぜかというと、イスラエルはパレスチナ人をその地域から追い出したいので、ハマスの攻撃を利用したのではとのことだ。」「AALAの学習会で、イスラエルの右翼の考えでガザのパレスチナ人を南のシナイ半島に追い立てることを主張していると言っていた。」「1993年のオスロ合意をクリントンが仲介をして、アラファト・ラビンが翌年ノーベル平和賞を取っているが、ラビンが暗殺される。この時は平和的に解決の合意をするが、実現しなかった。」「ネット情報で、なぜハマスがイスラエルを攻撃したのか。それはプーチンの陰謀だという説がある。ウクライナ侵攻でロシアが不利になっているから、世界の目をガザに向けさせ、ハマスが攻撃すればイスラエルが虐殺のようにやるのは分かっている。そうすると国際世論はイスラエルを非難するしアメリカが不利になる。それはすでにスターリンがやった手法だ。それをプーチンが学んだのでは。」「武器供与も、イスラエルへの対応が加わり、ウクライナへの予算が通らない状況がアメリカで起こっている。それでウクライナが現在苦戦をしているね。」
12月8日、静岡市内において12月号を使った「学習の友」学習会が開催されました。
今月の特集記事「崩される暮らしと権利―ストライキで社会を変える」冒頭、「岸田政権の労働政策をどう見るか?」(本久洋一國學院大學教授)を読合せ討論しました。政府が打ち出した「三位一体の労働市場改革」について、「一言でいうと、現行の雇用慣行とくに正社員制度や終身雇用慣行を破壊することによって、雇用の流動化を実現しょうとするものです。」と指摘します。次に「三位一体」の中身を、①リスキングによる能力向上支援、②個々の企業の実態に応じた職務給の導入、③成長分野への労働移動の円滑化、と分析しています。その上で、①について、政府が「構造的賃上げの第一の柱」としたのは、「低賃金の要因を主に「労働者の職業能力が低いことにあると見ている」と指摘します。②については、ヨーロッパのジョブ型雇用とは全く違い、ジョブ型(職務限定)雇用で、当該ジョブが技術革新で陳腐化したときは、簡単に解雇できる仕組みの導入と見ます。また、解雇の先が①のリスニング対応となる仕組みも見えて来ると言います。③については、「職安行政を雇用の流動化を主眼に組み直す」ものと指摘します。 次に、厚労省の「労働基準法改革」の提案を分析します。一つ目は労働時間規制を「働き方の多様化に適合的に規制方法を柔軟化する」というもの。「生産現場の作業員など」でない「サラリーマン」は、自己管理(業務・健康の)を「支える」とし、「労働時間は自己責任?」と思える提案となっています。二つ目はフリーランス(請負、業務委託)を労働基準法の対象に含め、原則として実労働規制を外して、「裁量労働制」、「高度プロフェッショナル制」を前提にした新たな労働時間規制を主軸として普遍化するとし、「従来と同様の働き方をする人」を例外として、実労働時間規制が適用される。これらが近未来にめざす提案となっているとのことです。 討論では、次のような意見がありました。「ジョブ型雇用は、賃金を下げるとは聞いていたが、ここでは仕事が古くなったら解雇して、新しい変えるようにするというのが狙いということだね。」「それは、最初からの狙いだ。もともとは、限定正社員制度というのがあったが、あまり広がらなかった。それをジョブ型と言い換えた。だから、ヨーロッパのジョブ型とはぜんぜん違う。成果主義そのものだから。」「フリーランスを労働基準法の対象に含めると言うと、何か良いことのようだが。」「逆にフリーランスの状態を当たり前にしようとするものだ。」「労働者と認めるが、時間規制はないよということか。」「それを標準にする。ちゃんと場所と労働時間を守って働く人を例外的にする「それを標準にする。ちゃんと場所と労働時間を守って働く人を例外的にするわけだ。」「時間規制がなくなるのが原則で、現場の人しか規制しないとゆうふうに変えようと言う事か。」「コロナでホワイトカラーがホームワークになった。それを標準にしちゃおうということだよね。」「労働基準法の考え方を根底から覆す考え方だ。」「これではもう労働基準法ではない。」「そうだ。ただまだ厚労省の研究報告の段階だが。」「2000年代に労働契約法ができ、雇用関係は契約法に移った。そうすると基準法は罰則があったが、契約法はない。民事的な解決となった。それを更に進める動きだ。規制から逆の方向に行こうとしている。」「現場の力関係にまかせるということでしょう。圧倒的に労働者が不利になるのは分かり切っている。」「組合があるところは、多少悪い組合でも一応力関係としてはあるわけだ。ところが、組合が無いと会社の言いなりとなる。」「強制労働と最低限の規制はするが、あとはない。」「今もほとんど強制労働状態のところがある。」「本人が辞めたいと言っても辞めさせないとかね。」など、恐ろしいような近未来を、政府は考えていることがわかりました。